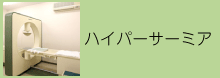全体朝礼より
更新日:2025/07/04 11:14 カテゴリー:朝礼
院長のタイトルは「暑熱順化と選ばれる病院を目指しましょう」でした。
常務の講話「約束の時間」より
皆さん、おはようございます。
院長からもお話がありましたが、本当に暑くなりました。先日ゴルフに行った時のことですが、身体が暑さに順化していない上に睡眠不足でプレーしていたところ、後半へばってズタズタになってしまいました。体力を過信しないように気を付けたいと思いました。 皆さんも体調の変化を見落とさないよう気を付けて業務にあたってください。
さて先日ネットを見ていたら「8時10分前に集合してください」と言われたら何時に到着しますか?という質問に対して最近の若者世代は、「8時くらい」や「8時7分」と答える人が多いという記事が出ていました。私たち世代では5分前行動が当たり前ですし、何かあったらいけないから余裕を持つ意味での前と解釈し7時50分に集合しますが、これは単なる勘違いではなく、スマホ世代ならではの時間感覚や、世代ごとの言葉のとらえ方が関係しているようです。
街頭インタビューでは、10代から20代の約6割が「8時~8時9分」と答えたという結果が出ているそうです。デジタルツールの発達とともに育った世代において、時間とは感覚ではなくて数値かもしれません。たとえば地図アプリを使えば目的地までの到着時間も分単位で把握できますので8時5分集合でも全く不都合はないわけで「時間を正確に伝えてほしい」と要望があったそうです。 言葉通りに受け取ることがスタンダードになっているからこそ、察してより明確に正確に伝えることが求められています。たとえば「7時50分集合ね」と具体的に伝えたり、「8時集合だけど早めに来てほしい」と補足したりすることで、誤解やすれ違いはぐっと減らせます。世代を越えてスムーズに気持ちが伝わるよう、少しの工夫と歩み寄りが、よいコミュニケーションのカギになるのかもしれません。
たとえば私がこのデータを月初までにまとめてほしいと依頼したとします。3日にはできているだろうとの思惑が、受け手の方が月初だから5日くらいでいいだろうと思ってしまうとそこにずれが生じて、仕事が遅いとの評価になったりします。 正確に伝えることで無駄な誤解が生じないように心がけましょう。
更新日:2025/06/02 10:47 カテゴリー:朝礼
院長のタイトルは「梅雨時のマイナスイメージを打破しましょう」でした。
常務の講話「目標を意識する」より
皆さん、おはようございます。
先月、過程を楽しみましょうというお話をしましたが、ある研修の案内にイチロー選手の練習に対する取り組み方が紹介されていました。興味を持ったので調べてみたら10年以上前の致知の記事にありましたのでご紹介します。今はイチローより大谷選手や千賀選手が旬でしょうが参考までに。
イチロー選手と言えば、努力が作った天才とか徹底してルーティンを守るということが有名ですが、若い時のイチロー選手のバッティングピッチャーをしていた奥村幸治によると、「彼はいかなる場合にも、試合で最高のパフォーマンスを発揮できるようにと、自分ができる努力を高い境地で積み重ねてきた。しかし常にハードな練習していたのかというとそうではない。例えばシーズン中に調子が悪くなると、試合後にもバットを振っている選手の姿をよく見かける。 ところがイチロー選手の場合、試合前のフリーバッティングと試合中以外にバットを握ることはほとんどなかった。それよりも身体を休めることが大切だとわかっていたからだ。
一方、自主トレーニングの期間や春のキャンプに入ると、イチロー選手はピッチングマシーン相手に3時間でも4時間でも黙々とバットを振り続ける。なぜそれほど長く打ち続けることができるのか。イチロー選手に聞いてみると、こんな答えが返ってきた。 「最初から長い時間打とうとしているわけではありません。ただ自分にはその日にやらなければいけない目標があって、その目標をクリアしようと思って打ち続けていると、3時間でも4時間でも集中できるんですよ」 彼はこうも言っている。「目標がないのに練習することって意味がないでしょう。それならいっそ身体を休めたり、 気分転換をするほうがいいと思いませんか」と。ただ漫然と数をこなすのではなく、自分はこれを掴みたい、この目標を達成したいという思いがあるから練習に向かう。そのために一球一球に明確なテーマと目標を持って臨むからこそ、イチロー選手は信じられないような集中力を発揮できた。イチロー選手が一流選手たる所以が、こうした努力の仕方の差になって表れている。」
小さな目標を立ててクリアしていくこと、例えば朝出勤して「気持ちのいい挨拶をする」という目標、職場に入ってすぐに「その日の予定や仕事の段取りを確認する」など。YES、YESの積み重ねは、過程を楽しむことにもつながります。その結果として今日はいい一日だったとなるのではないでしょうか。
技能実習期間を終えられたリーさんとアンジーさん、お二人ともお国に帰ってからも日々目標をクリアして、笑顔あふれる末広がりの人生を歩んでもらいたいと思います。
更新日:2025/05/08 9:53 カテゴリー:朝礼
院長のタイトルは「病院運営について」でした。
常務の講話「過程を楽しむ」より
皆さん、おはようございます。
新年度で昇格した人はそれにともない昇給していますが、定期昇給は例年通り5月支給の給与からになりますのでご連絡しておきます。支給日までに少しでもいい方向に進んでいると病院の財布の紐も緩くなると思うのでGW明けから早速頑張っていただきたいと思います。
ところで3人の男が舟釣りに行った時の話です。釣果は釣り人の腕だけではなく、海の状態やポイントによって大きく変わるようですが、思うように釣れない時、釣り人Aは、仕掛けを変えたり、餌を変えたりその場でいろいろと工夫するそうです。釣り人Bは、魚群探知機を覗き込みながらもっと魚のいる場所を探しましょうと船長に進言します。釣り人Cは、起きていると船酔いするからと誰かが釣れるまでじっと寝ていて、釣れ始めるとその仕掛けを真似て釣りを始めるそうです。
さて皆さんはどのタイプでしょう?同じ結果を求めるにしても過程を楽しめた方が面白味があり、達成した時の喜びも大きいのではないかと思います。
「過程」を楽しむことの心理学的効果として下記のようなことが言われています。 1.フロー状態への没入 最高のパフォーマンスを引き出す没入感 時を忘れるほどの深い集中 内側からわき上がるモチベーション 2.自己効力感の醸成 着実な進歩の実感 主体性の獲得 チャレンジ精神の向上 3.精神的回復力の向上 失敗に対する耐性の獲得 長期的視野の育成 ストレス耐性の強化
新年度に設定した目標に向けてスタートしたばかりですが、PDCAを回しながら過程を意識しましょう。そうすることでチームや自分の成長を感じられるようになるのではないかと思います。そしてそれは達成感となり、皆さんの笑顔につながっていくと思います。
更新日:2025/04/03 14:56 カテゴリー:朝礼
院長のタイトルは「結和会発足17年目」でした。
常務の講話「役割を自覚する」より
皆さんおはようございます。桜も満開となりました。病院の片隅に植えた小さな桜の木もわずかながら花を咲かせてくれて安心しています。
さて今日から新年度です。新たに7人の新入職員とめでたく復職してくださった2人を加え、新体制がスタートします。 新たに役職に就く方も多く、年度替わりで係が変わる方も多いと思います。それぞれが新たな役割を背負うことになります。
私自身も、父が亡くなった11年前に望んだわけではありませんが、お寺の総代、農協の委員など本業とは全く関係のない役割を背負うことになりました。家では俊野家12代目の役割として神棚・鬼門・裏鬼門・仏壇・お墓の管理を行うようになりました。今朝も1日なので神棚と鬼門・裏鬼門をお祀りしてきました。父がこんなふうにしていたなと見様見真似で始めましたが、いつからか役割として自覚し、家を守っていただいているという感謝の気持ちをもってお祀りするようになっています。
以前「ぶる」のではなく「らしく」しましょうとお話ししたことがあります。「役を演じる」というお話もしていますが、立場を自覚すれば行動は変わってきます。 昨日まで勉強しなかった子供が、小学生になったからと机に向かうようになったり、弟が出来た子供がお兄ちゃんだからと我慢できるようになったりすることもそうです。 役割性格が加わることで人間性に巾が出てくるのではないかと思います。新年度を契機にいろいろな役割にチャレンジしていただけたらと思います。
まずは「笑顔のあふれる西病院の職員らしく」を自覚して頑張っていきましょう。
更新日:2025/03/03 13:53 カテゴリー:朝礼
院長のタイトルは「満足度」でした。
常務の講話「経験から学ぶ」より
皆さんおはようございます。今空気が乾燥していることもあり各地で山火事がおきています。この間のロサンゼルスでは3週間も燃え続けたそうですが、正直いってロサンゼルスと日本とでは気候が違うからだろうなと対岸の火事と思っていましたが、岩手や長野での山火事も大変なことになっているのをみると他人ごとではなくなってきました。
枯草やごみを燃やしたことが原因となった事例もあるようですが、そうなるとぐっと身近で現実味をおびてきます。
実は土曜日に以前剪定した庭木を、雨が降る前に燃やしてしまおうと田んぼに運びました。幸い風もなくチャンスだと思い火をつけましたが、よく乾いていていたのでいつも以上によく燃えました。いつも灰が風で住宅地の方に飛んでいかないように風向きに注意して燃やしています。そして火が下火になってくるといったん家に帰って完全燃焼した頃を見計らって水をかけに戻るのですが、あの大規模な山火事を見てしまうと田んぼの中とはいえ、万が一近くの家に飛び火でもしたらと大変だと思い、燃えつきるまで田んぼから離れられませんでした。一番近くの家は薬局長の家なので尚更のこと気を遣いました。
また、さきほど院長からお話がありましたように、コロナのクラスターを経験したことで対応力が向上し、それ以降のクラスターが大きなものにならずに済んだのだと思います。
火の始末にしてもそうですが、意識が強くなれば、自然と行動が変わります。院内で起きた事象は各部署で共有し、自分事として意識することでそれぞれがしっかりとした対策をとれるように努めましょう。
それが院長のおっしゃる、患者さんが過ごしやすい「笑顔のあふれる病院」につながっていくと思いますのでよろしくお願いします。
更新日:2025/02/05 9:43 カテゴリー:朝礼
院長のタイトルは「違和感の情報共有」でした。
常務の講話「健康は内、ウイルスは外」より
皆さんおはようございます。例年立春の前日である2月3日が節分ですが、今年はうるう年による調整のためか、昨日2月2日が節分でした。
私が総代をしている瑞応寺でも豆まきの行事があり60人くらいの檀家さんが集まっていました。去年は、ほぼ100%の方がマスクを着用していましたが、今年は、半数くらいでした。街を歩いていてもマスクを着用している人は減ってきている印象です。やはりこういう油断が、なかなか感染が収束してくれない要因になっているのだろうなと感じました。
私が帰宅して、コートを脱いで着替えて手を洗いに行くと、家内から「帰ったらすぐに、コートを脱ぐ前に手を洗うのが常識でしょ」と指摘されました。感染対策上その通りだと思いながら、つい「コートが濡れて洗いにくいから仕方ないじゃないか、玄関に洗い場があるわけじゃないんだし」と言い訳をしました。こういった自分の都合でルールを変えてしまうようでは、完全な感染防止対策は取れなくなってしまいます。 玄関でコートを脱いで洗面所に直行すればいいのでしょうが、私の理想は、「ただいま」→「おかえりなさい」と家内が迎えに出る → コートを脱ぐ → 「今日もお疲れ様でした」と言いながらA2careをコートに噴霧しクロゼットにしまってくれる → 私は気分よく洗面所に手洗いに行く
テレビのワンシーンにありそうなこんな感じです。なにはともあれ感染対策を完全なものにするためには、勝手に手順を変えたりしないでマニュアル通りに実行することが大切だと思います。
皆さんはこんなことはないと思いますが、ほかの事例でもマニュアルに沿っているか確認して間違いないように実行していただきたいと思います。またほんのちょっとした手助けや、改善でスムーズに実行できることも多々あろうと思います。手助けが必要なことがないか気配りをし協力できる体制をとることも重ねてお願いしたいと思います。
因みに私は、ドラマのようなシーンは期待せずに、帰宅したらまず手洗いに直行しようと思います。
更新日:2025/01/06 9:07 カテゴリー:朝礼
常務の講話「 「笑顔」の秘訣はコミュニケーション」より
皆さん明けましておめでとうございます。
例年院長の講話から始まりますが、今朝がた咽頭痛があり検査したところコロナ陽性でした。インフルエンザも相変わらず猛威を振るっていますので皆さんも体調管理に気を付けてください。
また今年は水曜日始まりということもあり正月からの勤務の方が多かったと思いますがお疲れ様でした。ありがとうございました。
さて毎年、年頭に今年の目標を考えるのですが、今までも本を何冊読むとか、体力維持のためにトレーニングをするとか目標を立てるのですが中々達成できていないのが現状です。今年は、当院の理念に基づいて、「笑顔のあふれる生活」を目標に掲げようと思い、どんな時に「人は笑顔になるのか」と調べてみました。
その中で中国の昔話に、「天国にいる人は、長い箸で食べ物をお互いに食べさせあい豊かに暮らしているが、地獄の人たちは、自分で食べようとして長い箸が口に入らず、食べ物はあるのに餓死してしまう」という話があります。人のために自分ができることで人助けをしていけば、回りまわって自分も助けられ笑顔にしてくれる。というものです。これが当院の求めている「笑顔の連鎖」だと思いました。
事業継承をした2009年入院患者数は57人でしたが、地域の患者さんを広く受け入れよう、そして急性期から在宅までの入院が必要な患者さんに当院を選んで頂けるよう寄り添った看護を提供しようと努め、8か月後には80人を超えていました。2014年8月には、一般病棟39人療養病棟57人となりました。
地域の人を笑顔にしようと働きかけたらいつの間にか患者さんが増えていました。現在より少ない社員数での受け入れでしたので、これでは職員の皆さんが疲弊してしまうからと職員の増員を行ったわけです。営利を追求するのではなく人のため、社会のためになることを一生懸命して大きな笑顔の輪を作ることを目指していきたいと思いました。
話を戻しますが、人を笑顔にする10の方法によるといいコミュニケーションが取れる環境にいることが一番のようです。具体的には ①笑顔で話す ②面白いことをいう ③ポジティブなことを言う ④上手にほめる ⑤美味しいものをプレゼントする ⑥頑張っている姿を見せる ⑦その人のために何かしようとしていることを伝える(言葉・行動) ⑧夢や目標を語る ⑨励ます言葉を言う ⑩サプライズを行う だそうです。こんなことを意識して家族、そしてここにいる結和ファミリーの皆さんと良好なコミュニケーションをとり笑顔で過ごしたいと思います。
一年間よろしくお願いいたします。
更新日:2024/12/04 15:41 カテゴリー:朝礼
院長のタイトルは「創意工夫」でした。
常務の講話「今さらコロナ」より
今さらながら、初めてコロナに感染してしまいました。熱が出たものの全く感染経路に思い当たるところがなく、風邪で発熱したのだろうと思いながら、念のためにと検査をしたらまさかの陽性でした。離れに隔離の準備をしながら、無症状だった家内にも念のために検査をしたところ陽性でしたので、そのまま隔離されることなく自宅で過ごしました。人に感染させなくてよかったなとつくづく思いました。
ところで週末はバスケ仲間の忘年会で東京に行ってきました。
夕方の山手線では半数以上の人がマスクをしていましたが、帰りの10時半くらいの時間では2~3割の人しかマスクをしていませんでした。仲間内だから大丈夫という意識なのでしょうか?また感染が拡大しなければいいなと感じました。
またバイクスは現在1勝18敗と最下位に沈んでいます。まだ1試合もフルメンバーがそろって試合をしていません。そんな中で選手たちは一人一人がチームコンセプトをより理解し求められるプレイをマスターしようとしています。全員そろっていればそれぞれのポジションでの技術を高めていたのですが、ガードが抜けたりセンターが抜けたり、つなぎのボールハンドラーが抜けたりするので、それをどうカバーするかが課題となり本来の役割以外のプレイにも練習に励んでいるようです。
もっと楽しんでバスケをやったらと三男に話したとき、「バスケは今でも好きだけど小学生の時以来、楽しいバスケはやったことがないよ。」「もっとうまくなりたい。ブースターの期待に応えたい。そのために人より練習するし、オフの間にも体づくりをしているんだ。」と話していました。
当院でも患者さんが少ない時、丁寧な行き届いた看護が出来ていると思います。それに慣れてしまい患者さんが増えることが苦痛になるようでは本末転倒です。満床近くなっても同レベルの看護が提供できるように理想の看護力を身に着けて、院長がおっしゃるように地域から認められる病院になっていけるよう頑張りましょう。
更新日:2024/11/06 10:48 カテゴリー:朝礼
院長のタイトルは「衣替え」でした。
常務の講話「タイムアウト」より
皆さんおはようございます。
11月になり、さすがに秋らしくなってきましたが寒暖差のせいか中々風邪が抜けきりません。皆さんも体調を整えてこれからに備えてほしいと思います。
先日、Tリーグ(卓球のプロリーグ)の試合が松山で初めて開催されました。日本生命VS木下アビエル神奈川の試合で、日本生命は早田ひな選手、木下アビエルには、張本美和選手や木原美悠選手等オリンピック選手が在籍しているので、楽しみにして観戦にいきましたが、残念ながら早田選手は故障で来ていませんでした。しかしテレビで見るよりすごいスピード感で、私には1球も返球できないのではないかというくらいのスピードボールを打ち合っていました。
ところで卓球にもタイムアウトがあります。バスケットボールではタイムアウトは、前半2回、後半3回各1分間とることが出来ます。Bリーグでは、これに加えて2Qと4Qに90秒のオフィシャルタイムアウトがあります。卓球では、5ゲームマッチや、7ゲームマッチでも1試合に1回しかタイムアウトを取ることが出来ません。
したがって取るタイミングが重要になります。私が観戦した試合でも、競り合ってここを取ればというタイミングでタイムアウトを取ったり、一気に相手に流れが行きそうなときに早めにとったりしていました。そしてタイムアウト後のプレイで一気に流れを引き戻すこともありました。いったいどんな指示をしているのか知りたいなと思いました。
バスケットでは、タイムアウト時には、フォーメーションの確認や徹底するプレイの確認をすることが多いようですが、チーム5人が正確に理解しないと成立しないプレイがあるので日頃の練習での意識が大切なようです。
先ほど院長からお話がありましたように、今当院では、9月中旬から患者数が減少したまま推移しています。まさに病院としてタイムアウトを取るタイミングだと思います。「入院を希望される患者さんを速やかに受け入れる。また受け入れた患者さんを適切に看るための看護力・介護力を発揮しよう。」これが今回のタイムアウトの主旨です。入院患者数88人、透析患者数167人の目標を年内には回復したいと思っています。
チャレンジしなければ何も結果は生まれませんのでよろしくお願いします。
更新日:2024/10/03 10:34 カテゴリー:朝礼
院長のタイトルは「コミュニケーション」でした。
常務の講話「大谷選手のコミュ力」より
皆さんおはようございます。
例年ですと、ネクタイを締めて登壇する時期ですが、今年は暑すぎてもうしばらくクールビズを続けさせてもらいます。さきほど院長からお話がありましたように、これから4月の新年度に向けて、新しい体制かつより良い体制づくりに向かって前進していかなくてはなりません。
昨日メジャーリーグのレギュラーシーズンが終了しました。ご存じのように大谷翔平選手は、今シーズンは打者に専任し、ホームラン54本、盗塁59個で1位、打率0.310で2位あわや三冠王かという大活躍でした。投手としてのリハビリをしながら、打者としての調整を行い、出した結果ということを考えると、本当にすごいことだと思います。
テレビでも毎日のように大谷選手の活躍が放映されていましたが、私が特に感心したのは、コミュニケーション能力の高さです。バッターボックスに入るときに審判と何やら会話をしていたり、出塁した時にも相手チームの選手から声を掛けられ、会話しスキンシップをしている姿がよく映っています。
50号本塁打を打った時にも、球場全体がお祝いムードで盛り上がっているときに、喜びの姿と同時に相手チームに試合を中断して申し訳ないという様子で目配りをしていました。もともと大谷選手は、試合中でもグランドに落ちているごみを拾ったり、誰にでも礼儀正しく挨拶したり、ファンにも優しい選手だなと思っていましたが、ああいった自分のためのセレモニーの場面でさえ相手をリスペクトした行動がとれるのは、本当に素晴らしい人だと思います。
誰からも愛される大谷選手のようにとは、簡単ではないかもしれませんが、新しい組織・風土を作り上げていくためには、相手をリスペクトしコミュニケーションを取り合うことが不可欠だと思います。笑顔とともによろしくお願いいたします。