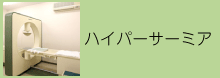全体朝礼より
更新日:2017/11/14 16:51 カテゴリー:朝礼
院長のテーマは「感染予防について」でした。
役を演じる
皆さん、おはようございます。
先日、芸人のキンタローとロペスが社交ダンスの世界大会に出場するという特番をやっていました。世界のトップレベルが出場する大会が近付いているというのにお互いの息がもう一つ合わないで伸び悩んでいました。そんな時コーチが、ロペスに合わせようと気を遣うより理想のパートナーの役を演じなさいとアドバイスをしました。すると別人のように伸び伸びと踊れるようになり息も合うようになりました。
私も最初に役職をいただいた時に、上司から「昨日まで仲間だった人間が今日を境に上司になる。しかし言わなくてはならないことは上司として妥協なく伝えなくてはならない。そんな時には役職者の仮面をかぶれ。」と言われたことを思い出しました。
皆さんも日頃、委員会であったり西友会であったりまた職場外でも役に任命されることはあろうかと思います。自分に向いていないとか、仕方なく引き受けたんだからこれ位でいいだろうとか思わないで役に徹することをお勧めします。
自分が芯から変わるのはすぐには出来なくても、役を知りそれを演じることはできると思います。そして自分自身の幅を広げていきましょう。
更新日:2017/10/04 15:32 カテゴリー:朝礼
院長のテーマは「標準予防策の大切さ」でした。
捨離と整理
おはようございます。衣替えの時期がやってきました。
先日、管理棟のフロアの張替があった際に、不要なものを処分しようと整理をしたら思いのほか沢山ありました。
この際、衣替えをきっかけに整理しようと思い、レースの参加賞でもらったり息子達がくれたりして箪笥に入りきらなくなっているスポーツウェア等を仕分けしてみました。ところが迷いなく捨てようと思えたのは3枚くらいしかありませんでした。これでは意味がないと思い、絶対に必要なものとそうではないものに分類してみました。すると以外に絶対必要と思うものが少なかったので、残りの中から第二次予選を実施し一部を繰り上げるようにしたら予選落ちしたウェアがなんとゴミ袋2杯分もありました。
とりあえず置いておくという考えでいるとだんだん整理が難しくなりますし、必要なものをすぐに取り出すことも難しくなります。パソコンでも気がついたらデスクトップがアイコンでいっぱいなんてことになっていませんか。
種類別に分類するなどしても不要なものが多いと整理がつきません。何を残して何を捨てるかと考えると自然に整理が出来ると思いますし、時間も効率的に使えるようになると思います。
更新日:2017/09/06 13:02 カテゴリー:朝礼
院長のテーマは「季節に合わせたケア」でした。
心施
皆さんおはようございます。9月に入りました、今日は防災の日ですがちょっと違ったお話をします。
先日七つのお布施についての文書を配布し、ペットや孫にはできるのにと書かせていただきましたが、大きな勘違いでした。特に5番目の心施(シンセ)が出来ていないことを痛感しました。
というのは昨日朝起きるとうちのトイプードルのルーくんがいつもより甘えて身体を摺り寄せてきたり、顔を嘗め回したり、さらにはゴロンと横になってお腹を見せるので、「今日は特にかわいいな、ママよりパパが上だと気づいたかな」と喜んでかまってやっていました。しかしその後も妙に私について回るので、家内が「オシッコしたいんじゃない」と言うのでいつもより早い時間でしたが散歩に連れて行ってみました。そしたらすぐに大量にオシッコをして、その後はいつものルーくんに戻ってしまいました。
私が自分に都合のいいように解釈をしていただけで、家内が台所で忙しそうにしているのを見て、代わりに私に連れて行ってくれとの訴えだったようです。当然ながら今朝は私には見向きもせず、起きたらすぐに家内の後追いをしていました。
うちのルーくんだけでなく大方のペットは残念なことに日本語が喋れません、自分の都合で好きなように解釈することが出来てしまいます。赤ちゃんに対しても同様で、ただ可愛いと思って見ているだけで、心を配って見ていなければなぜ泣いているのかなどもわかりません。
先ほど院長がお話した患者さんの痒みの問題にしても、的確にご自分の状況を説明できタイムリーにケアを受けられる患者さんばかりではありません。本当は痒いのに我慢してイライラしている患者さんもいるかもしれません。
表情やボディランゲージから気持ちや状態を読み取り、正しい対応ができるようになることが必要だと感じました。
誰もが他のために心を配り、患者さんも職員も誰もが笑顔のあふれる病院になったらいいなと思います。よろしくお願いします。

1.眼 施(げんせ) :やさしい眼差しで人に接する
2.和顔施(わげんせ) :にこやかな顔で接する
3.言辞施(ごんじせ) :やさしい言葉で接する
4.身 施(しんせ) :自分の身体で出来ることを奉仕する
5.心 施(しんせ) :他のために心を配る
6.床座施(しょうざせ):席や場所を譲る
7.房舍施(ぼうじゃせ):自分の家を提供する
更新日:2017/08/07 19:07 カテゴリー:朝礼
院長のテーマは「マンネリ化を排す」でした。
人生の最後にかかわる
先日、日野原重明先生が105歳でお亡くなりになった際、先生のご功績や生き方を文書にして皆さんにお配りしようと思いましたが、A4用紙一枚には収めきれなくて、結局名言集という形で配布させていただきました。ちょうどその頃新聞に「老衰死」増10年で3倍という記事が出ていました。
「その原因は、高齢者の増加が要因とされるが、背景には死因究明より、人生の最後を重視することで死を受け入れようとする本人や家族、医師の価値観の変化もあるようです。
在宅医療の普及で人々の意識は、死の原因ではなく、最後に至るまでの過程を重視する方向に変わってきたといいます。ドクターサイドから見れば、「老衰」と診断することに、診断を積極的に行わないことへの葛藤や病気の見逃しにつながるのではないかとの不安もあるようですが、本人、家族と医師との間で合意があり、穏やかになくなるケースは増えているのです。」とありました。
日野原先生は「いのち」とは、自分が自分の意図で活用できる「時間」であるという人生哲学をお持ちでしたが、まさにそういう生き方をされ理想的な死をお迎えになったと思います。
当院の第一の目的は、病気を治し在宅復帰をしていただくための医療・看護の提供です。しかし一方では終末期を迎えた患者さんの看取りも重要な役割となっています。そしてその中には認知症を発症し自分の意図が表現できなくなっている患者さんも多数いらっしゃいます。そういう患者さんをどう看ていくかということも今後の大きな課題となっています。
私の知人の中にもご家族を当院で看取らせて頂いた方もいらっしゃいますが、みなさん西病院でお世話になってよかったと言ってくださっています。
私たちの方向性は間違っていないと思いますが、さらに人生の最期をどう生きていただくかを考えて笑顔と医療・看護を提供していただきたいと思います。
更新日:2017/07/08 10:38 カテゴリー:朝礼
院長のテーマは「療養環境を良くしましょう」でした。
接遇と忖度
皆さんおはようございます。
先日透析学会に出かけた時のことですが、初めて行ったレストランで担当になったウエイトレスさんの表情が硬く、料理の内容や食材のことを詳しく聞いてみたかったのですが聞く雰囲気になれませんでした。
それに対して、初日に友人たちと行ったレストランではオーダーを取ってくれたウエイトレスが通りかかったときに飲み物が無くなりかけていたら「何か次の飲み物をご用意しましょうか」と笑顔で声を掛けてくれました。おかげさまで飲み物を切らすこともなく、大きな声でオーダーを通す必要もありませんでした。そのせいで少し余計に飲みすぎてしまいましたが。
また宿泊していたホテルをチェックアウトしているときのことでした。フロントの男性が気さくな人柄で世間話を交えながら応対してくれていたのですが、あるお客さんはタクシーを呼んでいて急いでいる様子でしたが手を止めて世間話を続けようとして、「急いでいるんだから早くしてくれ」と注意を受けていました。
こういった事例から、このところ話題になっている「忖度」という言葉が頭に浮かびました。忖度(他人の気持ちを推し量ること)が接遇に付加価値を与えるということが言えると思います。接遇の基本である笑顔や丁寧な言葉遣いはもちろんですが、忖度するためには相手を観察する姿勢が不可欠だと思います。
皆さんのマナーアップ評価表にもそうした事例が記載されています。これからもしっかり相手を観察して必要十分な対応ができたらと思います。
更新日:2017/06/06 13:54 カテゴリー:朝礼
院長のテーマは「出来ることを最大限にやる」でした。
接遇研修を活かす
皆さんおはようございます。
先日、患者満足度調査の結果を受けて接遇研修を行いましたが、私たち自身がスキルアップをしていかないといけない事項や改善の方向が明確になったと思います。またもっと患者さんの目線で考える必要も感じたのではないかと思います。
そんな中で設備面での不備など職員の皆さんでは対応のしようのないご不満もいただいていました。病院としても設備の更新のタイミングをみて改善をしようとしているものや構造上改善が不可能なこともあります。
病院として設備の改修や新たな機器の導入を検討している事項に関しては早めに情報を開示することでご不満を軽減していきたいと思います。例えば病棟の床頭台や照明に関しては検討の段階に入っています。
また設備や機器に関するご不満ですぐには対策を取ることが出来ない事項に関しては、私たちが出来る方法での代替案を一緒に模索検討していきたいと思いますのでよろしくお願いします。
更新日:2017/05/11 16:57 カテゴリー:朝礼
院長のテーマは「医療の質の向上を目指して」でした。
バックアップはマメに
皆さんおはようございます。
皆さんはパソコンや携帯電話のバックアップをまめに取っていますか?
実は先日、田をトラクターで耕していて時間を確認しようとポケットに手を入れたら、そこにあるはずの携帯がありませんでした。運転席をいくら探しても見つからないので田んぼに落ちたんだなって、でも後で携帯を鳴らしながら歩けば見つかるかなと安易に考えていました。ところがいつもの習慣でマナーモードにしていたため全く音は聞こえませんし、ローターで土を撹拌したため埋もれてしまったのか全く姿が見えません。初めて真剣にまずいなと思いました。
最悪の場合を考えてそれから出会う人には紙とペンを持ち歩き電話番号を書いてもらっていました。夜になって息子がiphoneを捜せというというアプリを使えばマナーモードになっていても音が鳴ると言ってきたので、10時を過ぎ周辺が静かになったころに田んぼに行ってそのアプリを起動させてみました。すると微かに音が聞こえてきたので周辺を探っていると何と無事な姿で土の中から出てきました。
いまだから笑い話のような話ですが、もし壊れていたり発見できなかった時にはまめにバックアップを取っていなかったことに大後悔するところでした。
万一のことを考えるときは最悪のところまで想定することは大切だと感じました。
皆さんも業務上のリスク管理はもちろんのこと私生活においても出来る限り予防策や事後の対策は考えておいてください。安全安心な病院づくりにつながっていくと思います。
更新日:2017/04/11 10:59 カテゴリー:朝礼
院長のテーマは「新年度を迎えて」でした。
9年目を迎えて
皆さんおはようございます。 結和会9年目を迎え人事異動多くありましたが、院長がおっしゃった様に特に事務部は藤森事務局長を迎え体制が大きく変わります。藤森事務局長は、浜松のご出身で、赤字経営で閉院となった浜松社会保険病院の民間譲渡にかかわり、新設したすずかけセントラル病院(309床)の運営に携わってこられました。しかし、しまなみ海道が大好きで老後は瀬戸内に住みたいとのお考えだったそうですが、縁あって当院に来ていただくことになりました。
新たな視点を加えることで、更に笑顔のあふれる病院となるよう発展していきたいと思います。
ところで皆さんは、ジャネーの法則というのを聞いたことがあるでしょうか。 「主観的に記憶される年月の長さは年齢の逆数に比例する」というものです。わかりやすく言うと5歳にとって1年は1/5ですが、50歳にとっての一年は1/50である、つまり50歳の人にとっての一年は過ぎ去ってしまえば5歳の子どもの10分の1に感じられるというものです。しかし実際に進行している時間は変化が少ないと長く感じられますし、反面毎日が新鮮で前向きに生活すると時の流れは早く感じられます。
冒頭にお話ししましたように今年度は人事異動も多く変化の年になると思います。毎日が退屈で長く感じられるのに、終わってみたら何だか短かったとならないよう、充実した仕事に取組み、やりがいのある一年だったと思えるよう頑張りましょう。
更新日:2017/03/11 12:59 カテゴリー:朝礼
院長のテーマは「選んで頂ける病院へ」でした。
不可逆になる前に
みなさんおはようございます。インフルエンザもピークを過ぎた印象がありますが、今年も猛威を振るったと言えるのではないでしょうか。
いくつかの施設ではアウトブレイク*させてしまい大変なことになっていましたが、当院ではアウトブレイク*させることなく見事に乗り切ったと思います。日頃の環境整備や日常生活においても感染のリスクを冒さない生活を心掛けるなど、感染予防に対する危機感や意識の高さのお蔭だと思います。
あるところでは、罹患している可能性を感じながらも責任感から出社し同僚に感染させてしまうという事例もあったようです。
不可逆という言葉があります。どうしようもなくなる時点のことを言うのですが、どうしようもなくなってからの努力(不可逆的努力)はいわば事後処理であり、生産性もなく苦労も大きいものです。
しかし当院では不可逆を迎えることなく速やかに部屋食に切り替えたり、来院者に対しても感染予防対策をとりました。そしてチームワークにより業務の変更にも円滑に対応し業務を遂行しました。こういった事例の積み重ねは院長がおっしゃるように当院が熟していくための基になっていくのだと思います。
これからも、どうしようもなくなる前に危機感をもち、手を打つ習慣を持つ。そしてそれをマニュアルの改善にいかし徹底を図る。より安全で快適な病院でありたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
*アウトブレイク 院内感染、集団発生のこと
更新日:2017/02/06 17:03 カテゴリー:朝礼
院長のテーマは「冬場の健康管理」でした。
寄り添って聞く
おはようございます。
皆さんも日ごろ聞く事の大切さを感じていらっしゃることと思います。マナーアップの自己評価表にも心を添えて聞く事で患者さんとの距離が近くなった等記載されています。
その聞くということについて興味深いお話がありましたのでご紹介します。
ある方が、職場での人間関係に悩んで「職場の教養」を出版されている倫理研究所の方に相談された時のことだそうです。
「○○さん、あなたは奥さんの話をきちんと聞いていますか?」と問われたそうです。職場の人間関係に悩んでいるのになぜ妻の話かな?と思ったそうですが…
「もちろんです、聞いていますよ。」
「そうですか。ではもし奥さんが『大嫌いな人がいて、殺したいと思います。』と言ったらなんて答えますか?」
「もちろん、そんなことをしたら大変なことになるよと答えます。」
「○○さんそうじゃないんですよ。『なぜそんなに嫌いなんですか…、じゃあ一緒に殺しに行きますか…?』と、もちろん本当に殺しに行くなんてことはありませんよ、でもこれが本当に聞くということなんです。」と言われたそうです。
寄り添って聞く姿勢を表した事例だと思います。恐らく自分の立場に立って聞いてくれたら、共感してくれたと感じたら少しは救われるということではないでしょうか。
そしてこうも言われたそうです。「○○さん家庭はトレーニングの場です。親子の関係・夫婦の関係がいい人は聞く姿勢が出来ている人、おそらく職場でもいい人間関係を築くことが出来る人だと思います。」と。
当院の看護部の理念である「笑顔を忘れず、こころに添える看護を提供します。」を実行するためにも聞くことは必要不可欠なことだと思います。
私も家庭はトレーニングの場と考えて、妻や娘の話をきちんと聞こうと思います。皆さんも家庭でトレーニングをして、病院ではさらに聞き上手になって患者さんに寄り添っていただけたらと思います。


 1.眼 施(げんせ) :やさしい眼差しで人に接する
1.眼 施(げんせ) :やさしい眼差しで人に接する